|
作家、黒澤はゆまさんの『なぜ闘う男は少年が好きなのか』の感想です。 現代ではあまり見られない男色(少年愛)について、時代や地域、人間や動物の様々な例をストーリー仕立てでわかりやすく取り上げている本。 少年愛の歴史的な意義も探ろうとしており、興味深いです。 また、著者の文章が非常に美しいため、この記事も熱がこもってしまいました。 |
なぜ闘う男は少年が好きなのか
最初に言わせてください

私はこれまで好きなった人は全員女性であり、私自身は(おそらく)異性愛者です。
しかし、この本を読んで目覚めました。(別に同性愛に目覚めたというわけではない)
何に目覚めたかというと、男色(少年愛)には男女の性愛とは異なったある種の「真理」の匂いがあることにです。
この本を読めば、男色というものが、文学、哲学、政治、芸術などの多方面に影響を与えた面白いエピソードを知ることができるでしょう。
しかし本書のもっとも重要なポイントは、歴史上の多彩なエピソードの面白さだけではありません。
男色の隆盛と衰退を描きながら男色の本来的意義を提示してくれるところに、本当の面白さがあるのであり、そこに著者の意気込みが感じられます。
洋の東西を問わず、戦乱の時代に決まって栄えた少年愛。
死を賭して戦う戦士たちの側近くに控える、あるいは金髪の、あるいはブラウンの、あるいは黒髪の少年たち──。
小姓、稚児、エローメノス、宦官、酒姫(サーキ)。
呼び名はさまざまなれど、それら美しい少年たちに戦士は何を求め、少年は戦士に何を与えたのか。
著者について
何を隠そうこの著者は小説家であり、男色をテーマにこれまで二冊の本を書かれています。
この本を読んでいて感じることは、全体として読みやすいフランクな印象でありながら、「文章が非常に美しい」ということです。
ですから、読んでいてどんどん引き込まれていき、もう止めることができずに、次のページをめくっていることが何度もありました。
男色とは
男色とは男性の同性愛を指す言葉ですが、この本では主に少年愛について書かれています。
少年愛とは、成人男性と少年との愛を言うのですが、少年といっても年齢は18歳を越えていたりするので、一概に”少年”とは限りません。
そして、歴史をみると同性愛者のみが少年愛を行うのではなくて、異性愛者が少年愛を好むということがしばしばありました。(奥さんがいながら、少年と愛を育むといったケースはよく見られます。)
現代では異性愛が「常識」となっている風潮がありますが、過去をみてみれば美しさは両性に属していたものでした。
「近代化という過程とは、かつて両性に属していた美という性質が、女性へと専門化してゆく過程である」
その言葉通り、かつて美少年が担っていた美、振袖のようにときに女性の側がそのファッションを取り入れることさえあった美は、すべて女性に簒奪されることになりました。
男色と仏教
さて男色と仏教の関係ですが、バッチリこの本の中でも紹介されています。
日本では、空海が日本に男色を持ち込んだ、という説があるらしいですが、あまりにも伝説が多すぎる人のため実際はどうかわかりません。
基本的に仏教では出家者に対しては「不淫」という性行為そのものに対する禁止が、戒と律の両方にあるため、本来的には男色もアウトです。
完璧に性欲を断つ、というあまりの厳しさへの反動もあってか、『律蔵(集団の規則が書かれている)』には、性欲を我慢しすぎたお坊さんの異常ともいえる行動が記されています。
猿と獣姦した、自分のアレが長かったから自分の尻に入れた、死んだ彼女の骨でアレした、などなど。
こんなに変態さんが次々にあらわれるのなら、仏教の修行って精神衛生によくないんじゃないのという気もしてきますが
というようなコメントも著者の方からいただいております…。
(性欲と修行とは切っても切り離せないところがあるので、いつか別の記事で書きたいです)
そんな初期の仏教から日本に仏教が渡ってきたときには、当然厳しい戒律がありました。
しかし、最澄が独自に戒壇を設けたために、日本仏教は世界でも珍しい、世俗主義の傾向が強い仏教となりました。(もちろんそれを後押しする日本文化もあったでしょう)
世俗主義とはいっても、当時はまだ結婚はできなかったので、ほぼ必然的に男色文化が華開くことになります。
日本仏教の男色
男色のターゲットになったのは「稚児(ちご)」とよばれる少年たちでした。
現代でも「稚児行列」とよばれる伝統行事で、お祭り化している地域もあるのではないのでしょうか。
稚児は師僧の身の回りの世話をする少年たちのことを指しますが、時として男色の対象にもなりました。
僧侶たちは稚児を寵愛しまくったのです。
鎌倉時代の僧、華厳宗の宗性は、弥勒菩薩の浄土とされる兜率天への往生を願って、
「男を犯すのは100人で終わりにする(本当はもっとしたいけど)」
とゾッとするような誓いを立てたりしていたらしい。
他にも、僧兵の武力を使ってまで、かわいい稚児を奪い合う様子などが書かれています。
また密教の儀式で神聖なものとされた「灌頂(かんじょう)」は相手が稚児になると、非常になまめかしいものになったらしいです。
下はドン引きエピソードかもしれませんが、少しだけ紹介します。
師僧と稚児は丁重な作法とともに床入りして、二人で“極楽”へ旅立った後、
師僧の無明火(あそこのことです)は萎えしぼみ、八葉蓮華にたとえるべき稚児の無垢清浄な法性花(お尻のこと)は開花します。
それは、仏の真実の教えと出会い、自らの本性に立ち返ったのと同じくまことに尊いことなのです。
……ノーコメントです。
(稚児灌頂について探したら、詳細がかかれたサイト様がありました。:稚児灌頂(ちごかんじょう))
日本で男色が廃れてきても、僧侶向けの陰間茶屋(男娼館的なもの)とかは残っていたらしいですし、仏教と男色はとても相性がいいものとして歴史上存在したわけです。
男色の衰退
この本を見ればわかりますが、男色は仏教だけでなく、様々な分野で世界中どこでもあったものです。
さらに、動物でも同性愛行動が確認されたのは1500種を超えているようで、特に、ゴリラは同性のみの群れを作り、性的に交わっていることが見られているそうです。
ここからも、一部の人々がいうような「異性愛がのみが自然である」という論旨は意味をなさないことになります。
ではなぜ男色文化は廃れたのでしょうか。
様々な影響が述べられていますが、やはりキリスト教は外せません。
「男娼となる者、男色をする者は神の国を相続できない(第一コリント6章9-10節)」と、聖書には書かれています。
その影響もあり、同性愛の弾圧はヨーロッパにおいてかなり厳しいものとなっていました。
キリスト教の影響下にあったヨーロッパに比べると緩やかですが、日本でも江戸時代中期から後期には廃れてきました。
その理由として、男の衣装の地味化に対する女性の衣装の豪華さ、そして早婚化が男色衰退の大きな要因として挙げられています。
「われわれはすべての文明において、男の灰色の過程を体験する」
動物界などはオスのほうが派手な格好をしていることが多いといいます。(クジャクの羽やライオンのたてがみ、鹿の角など)
たしかに、戦国時代の武将などは力を誇示するために派手な兜や衣装を着ていた武将たちがいました。
しかし争いがなくなり、大人の男が地味になるのに比例して少年も地味になっていきます。
そして早婚化も男色の衰退に拍車をかけました。
戦国~江戸にかけては、修行・鍛錬のため、三十~四十になっても結婚せず、男色をもっぱらにするのが男らしいといわれていました。
しかし、江戸時代中期頃からは二十代にはさっさと結婚し所帯を持つのが普通になりました。
逆に女性の装束は時代が進むにつれ、どんどん派手に豪華になっていきます。
男の衣装の地味化、それに反比例する女性の衣装の豪華さ、そして早婚化。
こうした現象は決して日本のみではなく、全世界で共通して見られたことでした。
そして、明治になると西洋的価値観に従って作られた法律によって、男色が全面的に禁止され、日本における男色は廃れていきました。
男色の意義
著者は男色の意義のついて、ゴリラ研究の第一人者の説明を用いて、鋭い考察をしています。
山極寿一教授によると、家族と共同体、二つの形式を両立させて集団を形成する動物は人間だけなのだそうです。
それは、家族が見返りを期待せずに奉仕し、身内を一番に考えるえこひいき(偏愛)の集団であるのに対し、共同体は平等あるいは互酬性を基本としたいわばビジネスライク(博愛)な集団だからだといいます。
偏愛と博愛のロジックは、お互いに矛盾するわけですから、動物が使い分けられないのも当然です。
確かに、家族とは血による強烈な区別意識によって形成されます。
それは「家族のためになら見返りを求めずに行動する」という感情を生み出しますが、同時に偏愛(えこひいき)を生み出します。
反対に、共同体では個人は抽象化された存在になり、代替可能な人物へと変化させられることによって、博愛(平等、互酬性、ビジネスライク)な取引関係になります。
そして、人間は生きるためにこの二つの矛盾した状態の解消を求められます。
著者はこのような、この矛盾の解消にこそ男色が発生した原因と意義があるとみています。
人類の共同体の起源をたどると、それは男だけの狩猟集団に行きつき、やがてそれが軍隊や国へとつながっていきました。
そして著者は、その集団の絆を貫いていたものこそ男色である、といいます。
本来的には家族に属すべき性愛関係を、共同体という全く異なる場所において実現すること。
それが家と共同体という矛盾を一つにつなげるために人類がとった行動でありました。
仏教で言えば師匠と弟子の関係も似たようなものです。
仏教では自分の名前をかえて共同体(サンガ、仏法を学ぶ場所)に入りますが、それは外から見れば、師匠と弟子は教えを提供する人と教えを請う人という取引関係が生じていると思うのが自然です。
しかし、実際には、そこには取り引きや見返りのない無償の愛が伴わなければなりません。
それは本書の中でも取り上げられる、「御恩と奉公」の関係にも似ています。
本来、御恩と奉公というまさにビジネスライクなものであるはずの忠誠の物語は、洋の東西を問わず、見返りを求めぬ無償の愛で満ちています。
タフでストロングな男たちの冒険と征服の物語であるはずの歴史。
実はその裏で巨大な歯車を動かしていたものは、男と男による、忠誠を偽装した愛だったのです。
戦国武将が小姓と男色関係を結んだことと、僧侶が稚児と男色関係を結んだことには無意識的にしろ共通したものがあるかもしれません。
少年が癒すもの
私は著者の言う通り、男色(少年愛)は単なる女性の代替品という見方を超えたものであると思います。
この記事の最初にも書きましたが、男色(少年愛)というものは同性愛とイコールではありません。
むしろ同性愛者・異性愛者という枠を超えて、流転するこの生において極めて純粋な形で発現する愛の形態です。
それは共同体において自己を象徴化せざるを得ない人間が唯一自らをとりもどす瞬間であったと思います。
著者は、オスカー・ワイルドが語った言葉を引いてこう言います。
「大人の男は知性を授け、少年は喜びと希望、そして人生の魅力を、彼の前に捧げます」
かつて戦場という世界の傷口に向き合う闘う男のかたわらでたたずんでいた、あるいは金髪の、あるいはブラウンの、あるいは黒髪の少年たち。
彼らが癒やしていたものは闘う男の傷だけでなく、世界そのものの痛みだったのでしょうか。
「闘う男」とは単なる戦士を意味しない。
それは、世界の傷口に向き合う者。
「なぜ闘う男は少年が好きなのか」
この問いをもって、この本を読んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 男色の感動・面白エピソード盛りだくさん。
- 男色が果たした意味がわかる。
- 劉邦とオスカーワイルドの話が好きです!あ、ソクラテスの話も・・・いや権九郎と甚之助の話も捨てがたい・・・

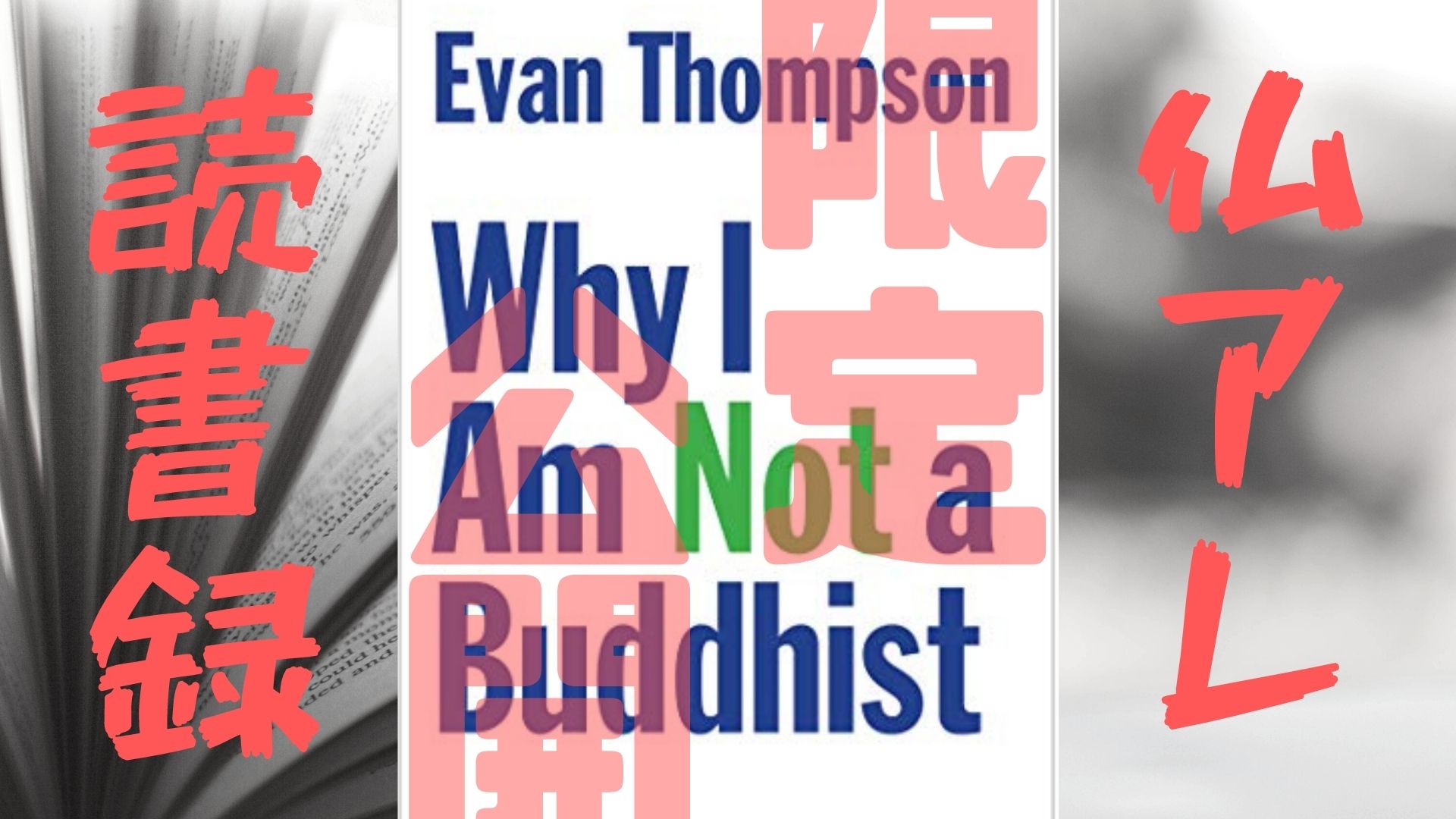




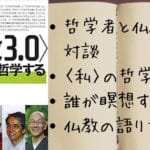

 「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
