|
この記事は、パブリックドメインとなった『大法輪閣版 澤木興道全集』を元にして読みやすいように再編集したものです。 昭和の時代に“最後の禅僧”と呼ばれた高僧の言葉をコメントと共に紹介いたします。 |
前回はこちら
朗読していただきました!↓
元旦に人事行礼といって、おめでとうと言う挨拶をする。方丈(住職)を前において香を焚いて「此日改歳(カイサイ)の令辰(レイシン)謹んで嘉悰(カソウ)の儀を伸ぶ、即日気運極めて寒し、恭しく惟れば(ウヤウヤしくオモンミれば)堂頭和尚尊侯起居万福(ドウチョウオショウソンコウキキョバンプク)」といってお辞儀する。「どうぞおまめさんで……」ということである。こんな肉体のごとき、体温計の上がったり下がったりする垢のついた体を、べつに大切にというのではない。真に仏道につかえる身を大切にというのである。

そこで何がめでたいかを工夫参究する。正月の工夫です。一番めでたいものになりたい。めでたくありたい。めでたくしたい。わたしは道元禅師の歳朝の上堂、元日の説法を紹介したいと思う。
歳朝の上堂(サイチョウのジョウドウ)挙す宏智古仏天童に住す(コす ワンシ コブツ テンドウにジュウす)歳朝上堂していわく歳朝坐禅万事自然(サイチョウのザゼン バンジ ジネン)心心絶待仏仏現前(シンシン ゼッタイ ブツブツ ゲンゼン)清白十分江上雪(セイビャク ジュウブン コジョウのユキ)謝郎満意釣魚船(シャロウ マンイ ウオをツるフネ)参(サン)師曰大仏拝読其韻(シ イワく ダイブツ ソのインをハイドクせん)良久曰(リョウキュウしてイワく)大吉歳朝喜坐禅(ダイキチ サイチョウ ヨロコんで ザゼンす)応時納祐自天然(トキにオウじて ユウをイれ オノズカらテンネン)心心慶快笑春面(シンシン ケイカイして シュンメンをエましめ)仏仏牽手入眼前(ブツブツ テをヒいて ガンゼンにイる)呈瑞覆山盈尺雪(ズイをテイし ヤマをオオう エイセキのユキ)釣人釣己釣魚船(ヒトをツりオノレをツり サカナをツるフネ)
宏智(ワンシ)という大徳がシナ浙江省(セッコウショウ)の大きな寺におられた。これが有名な天童山である。道元禅師もここで修行あそばされた。この宏智禅師の歳朝上堂の第一のお言葉に「歳朝の坐禅万事自然」とある。これはありがたいお言葉である。坐禅とはどんなものかというに、どんな学者も学問を捨て、金持ちは金を捨て、智慧者は智慧を捨て、弱いものは弱さを捨て、貧乏人は貧乏を捨て、一切を投げ出して坐るのである。ただ坐るのです。私がよく言う言葉であるが、自分になり切る。私になり切る。あなたがあなたになり切る。山が山になり切る。茶碗が茶碗になり切る。一切のものがそれ自身になり切る。それが坐禅である。
男なのか女なのか会社員なのか自営業なのか 大人か子供か妻か夫か。 そんなことは、坐っている自分と全く切り離して ただ坐ることを「自分になり切る」と言っています。 本当の自分といって、わかるのは今ここの自分だけです。 自分になり切るという自分とはなにか
自分になり切るという自分とはなにか
出る息がフーと出る。入る息がスーと入る。澤木がこうしてスッと坐った切りである。そうして限りない宇宙と一緒になっている。坐禅は宇宙の全景を宇宙の全景のままにしておくものである。茫々として限りないものを限りないままにして置き、手は手で足は足、鼻は鼻、頭は頭、ヘソはヘソでそのままにしておくことである。
昔ある男が、雪の朝まだ寝ていると、男衆が雨戸をガラガラとくり出して「旦那様、今日はえろう雪が降っておりますよ」「そうか、どの位か」「深さは五寸ばかりですが、幅は知れません」といったという話がある。
この幅の知れんのが宇宙の不可解であり、真理である。この幅の知れないのを幅の知れないままにしておく、それになり切るのが坐禅である。
その幅がなんぼあるかと、寸にとって歩くような愚かなことはしないわけである。その知れんままにしておるのが「万事自然」だ。富士の山を高いままに眺め、雲がかかったらかかったままに眺めて、それをどうもしない。
本分に安住している。かくかくのものが、かくの如く安住している。低いところが低く、高いところが高くて万事自然である。人間の体もこの通りで首は上に位し、足は下にいる。前後別あり左右定まる。こういうのが万事自然である。
各々その持ち場持ち場をまもって、素直にして少しも不平を言わず腹も立てない、調子づいてもいなければ悲観もしていない。如法に安住し、本文に安住しているのである。これがいつも私のいう「打ち方止め」である。
やんややんや騒ぎ立てるのをやめるのを 銃を構えた兵隊に「打ち方止め!」と 号令をかけることに例えた話を老師はよくします。 気に入らない状況をどうにかして良くしようと
気に入らない状況をどうにかして良くしようと
次回に続く!

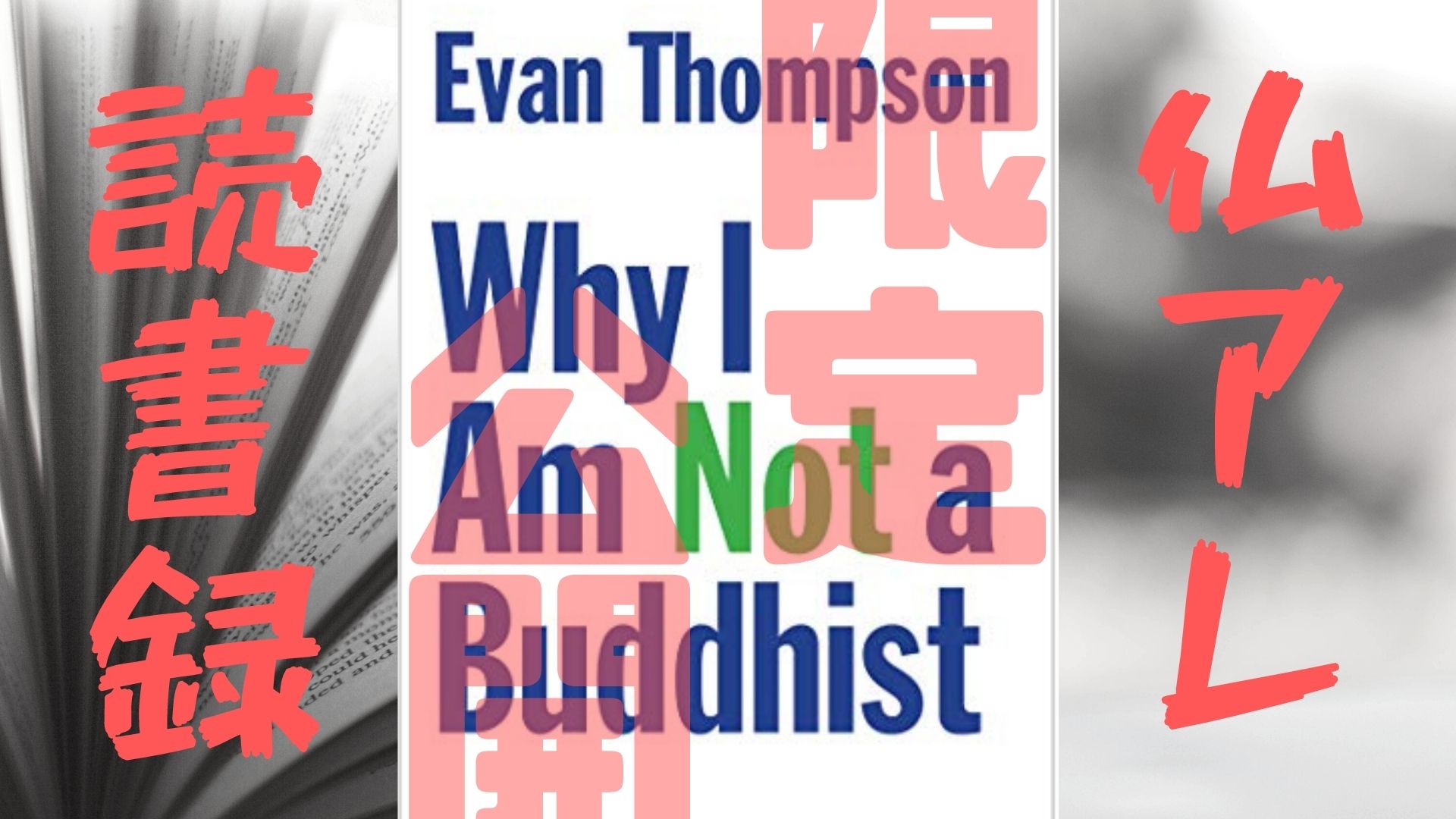






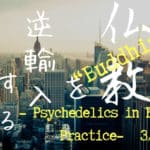
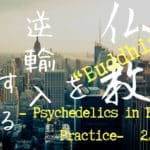
 「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
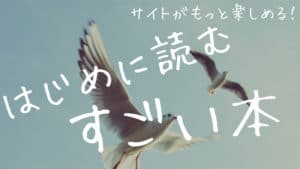
とりあげているので、難しい漢詩が出てきますが
読むのしんどいので読み飛ばしてもらっても大丈夫です。
なんとなく漢字の意味だけ想像してもらえれば。