|
浄土真宗の僧侶であり、宗教学者でもある釈徹宗さんの著作です。 釈徹宗さんは「NHK100分で名著」での解説など、 多方面でのご活躍で有名ですが、 ご本人の著作でも、宗教や仏教についてのわかりやすい説明と本質的な問題を扱っています。 『死では終わらない物語について書こうと思う』では、浄土真宗の日本における発展を踏まえ、 現代日本人が「情報」を偏重する一方で、徐々に失ってきた「物語」をキーワードとして 多くの人が自分自身の人生を見直す際に目をそらすことはできない問題を提示しています。 |
最重要キーワード「物語」
著者のキャラクターである“わかりやすさ”のイメージ通り、とても平易な解説と構成である本書ですが、そのイメージ通りの印象を安易に抱くと、おそらくは「浄土思想の簡単な解説書」のように受け取ってしまいがちだと思います。
しかし、タイトルにもあり、また著者が言うこの「物語」というキーワード。
見た目に反して、本書は実は決して単なるガイドラインではなく、「物語」をテーマに人がいずれ直面せざるを得ない人生における非常にクリティカルな問題を扱っています。
著者が言う「物語」とは、仏教にとどまらず、人文分野からの人生の探求においては避けては通れないものです。
現代社会を生きる我々は、ついつい情報に振り回されがちです。情報は消費されていくだけのものであり、決して我々の人生や後生を支えてくれるものではありません。
情報というのは、新しいものが手に入れば、それまでのものはいらなくなります。役に立たなくなるからです。使い捨てです。役に立つか立たないかが一つの目安になります。
これに対して物語は「一度それと出会ってしまうと、もはや無視することはできなくなる」、そんな性質をもっています。
著者の定義する「物語」とは、われわれが日々消費する単なる“情報”ではなく、個人の人生観をまるごと請け負うような強固な世界観のことです。
それは決して一部の人のみがもつ、特殊な思想や思い込みではないことに気をつけなければなりません。
基本的に本書では浄土信仰における各人の「物語」の受容の仕方を紹介しながら、その形を描き出しています。
おそらく著者のいう「物語」とは時代や場所、人の性質にかかわらず「人間が世界をどのように眺めるか、その説明と意味づけ」のことです。
つまり誰しもが個人個人の「物語」を持っているはずであり、それに自覚的か否かに関わらず
人生を送るうえで最大と言ってもいいほどの影響力を持つものが「物語」として扱われていることだと思います。
現代人のもつ「物語」とその貧困
おそらく日々の生活で「物語」を自覚的に意識することはほとんどないでしょう。
地域や親族コミュニティへのコミットが減り、個人の人生観が多様化する中では当然の現象です。
しかし実際に、その無自覚な「物語」が個人に対して、どのように機能しているでしょうか。
それを考えるためには「どう生きるべきか」「正しさとは何か」「何が大切なのか」と言った質問に対して答えるための、個人的「物語」を点検しなければなりません。
もちろん上記の質問に簡単に答えることはできませんし、これらは人生において、ほとんどの場合目をそらし続けても何とかなる問題です。個人の「物語」がこれらに答えられなくとも、なんとなく生きていける場合がほとんどです。。
しかし同じ「物語」であっても、例えば「今週は食べ過ぎたから、日曜日にランニングをしよう」と決めた場合
そこには確かな「物語」が成立しているはずです。
摂取カロリーは消費カロリーとのバランスを取るべきだ
肥満は健康に悪影響がある
エクササイズはカロリー消費以外の面でも身心に好影響をもたらす
空いた時間に有益な活動をすることは善いことだ
など、もっともらしい理由付けには、それを正しく、善いことだと感じる「物語」が必要不可欠なのです。
一見、科学的情報や個人的気分にのっとって行動しているだけのように思うかもしれません。
しかし、その情報や気分を「正しく、善い」とする根拠はおそらく、どこまで点検しても見つからないでしょう。
研究によって正しいとされているから正しいのだ、というのであれば、なぜその正しさを善いと思うのでしょうか。
個人的な意味づけを、一つ一つ、はっきりと行っている人がそれほど多いとは思いません。
「不健康な状態が単純に不快だから。容姿を損なうことで社会的価値が低下することが不都合だから」などと、いちいち考えている方はそう居ないでしょう。
大抵は「世間でそれが正しく善いとされているから」であり、その判断を生み出す世界観そのものが「物語」です。
では、この「正しく、善い」を導き出すことのできるあなたの物語は、いったいどの程度の働きを持つでしょうか。
著者は本書の中でこう語ります。
生と死が交錯する〈物語り〉が枯れている時代。一方では、終活を実践するための死生観を持たねばならない状況。我々は〈物語り〉を取り戻さねばなりません。
ここにあるとおり、本書で扱われるべき「物語り」とは“生と死”の問題を扱う事すらを可能とする「物語」です。
老いや病と直面し、死を直視せざるを得ない臨終にあたってもなお、説得力を増すような強固な「物語」です。
それを著者は、浄土真宗の特徴的“浄土思想”を踏まえて「死では終わらない物語」と名付けています。
死では終わらない物語
なぜ、単なる「物語」ではなく「死では終わらない物語」でなければならなかったのでしょう。
著者はそれを、我々はなぜ「往生伝的なもの(※臨終についての伝記)」を求めるのか、という問題において
「死では終わらない物語」がなければ、この世界を相対化することが出来ないから、と語ります。
人類学的に言えば、「来世」と「神」は〈この世界〉や〈私〉を相対化する装置、人類が生み出したこれ以上ない究極の装置です。
現代人にとって、「この世界」や「私」は、純然たる絶対的存在として確かに感ぜられます。
「この世界」の他に世界は無いし、「私」以外の主体は存在しないのがあたりまえです。
では、その唯一の世界が、唯一の私が、苦しみに満ち、救いようもない絶望にあふれてしまったらどうするべきでしょうか。
替えのきかない絶対的存在ですから、例えてみれば花瓶にさした一輪の花のようなものです。
その一つだけしかない花が醜くしぼみ、枯れてゆくとき。
その花に替えがないのであれば、枯れてゆく絶望感という現実につつみこまれてゆくことだけが結果として残るほかありません。
しかしもちろん、誰が考えても、“代わりの花を挿しかえればいい”と思うでしょう。
では、そうだとして、「世界」や「私」に代わるものが簡単に見つかるでしょうか。
そもそも、その絶対的なものが、相対化するとは一体どのような時でしょう。
それを著者は浄土思想の中での記述において明確化するため様々な例を本書で挙げています。
日本史における最も伝統的な「物語」の一つである浄土思想をそのように一つ一つ取り上げ考察することに
人生における「物語」の重要性と役割を見出すための有意義な価値があることは言うまでもありません。
今生での死との直面において、今生の相対化は「来世」という物語によって行われます。
人にとって「物語」とは現実の世界そのものである
「来世」という非科学的存在に納得がいくでしょうか。
その是非は置いておきます。本書でのテーマはあくまで「物語」であり、どの「物語」が優れたものであるかを決めるのは読者各人の努力を必要とするものだからです。
【「現世」の苦しみを「来世」による相対化によって救う】
という構造を見て、安易な現実逃避のように感じる方も多いでしょう。
しかし重要なことは、「往生伝」などで紹介される「願生者(極楽往生を願うもの)」にとって、「極楽浄土(来世)」とは単なる現実からの逃避ではなく、彼らの世界観における事実そのものであるという点です。
本書において語られる、浄土思想での現世の相対化とは、
「一輪の枯れゆく花を、存在もしない若く美しい花に代えられると妄信して、枯れゆく花の醜さと悲壮から目をそらす」
ことではなく、
「代わりの若く美しい花を確信することによって、今枯れゆく醜い一輪の花がその姿のまま味わい深い価値を持つ」
ような、現在を丸ごと救うポテンシャルをもった現実的役割を持つ物語のことです。
この生と死に直接かかわるような重大な意味づけを担うことのできる「物語」を
一体どれだけの現代人がもつことができるでしょうか。
※人間が思う「あたりまえ」も物語そのものです。お坊さんがよくいう「ありのまま」も、この物語と深く関係しています。
所感
「物語」の重要性は、お坊さんだけでなく宗教学や思想哲学などの人文学を学ぶ方であれば、考えることが多い問題だと思います。
その「物語」という一大キーワードを、しっかりと取り扱い、浄土思想と結びつけながら描き出す大変おもしろい一冊でした。
ただ、本書の終盤で語られる「物語」と「無我」についての考察には、禅宗の僧侶としては少し首をひねる部分もあります。
「無我」という仏教の前提的世界観は、その実践における納得において「物語」を“解体”すべきものです。
著者は無我と物語の両立不可能な構造に言及はしていますが、無我を“解決しない異物”として扱い、“死では終わらない物語”に沿って進むことを強調しています。
浄土真宗の教義としてあたりまえなことは重々承知していますが、その見方は、やはりちょっと一方的におもえます。
根本的事実として、仏教には「無我」があるため、浄土真宗(おそらく曹洞宗も)も含めた各宗派の「物語」とはその後に作られた独自の様式でしかありません。
修行の途上において必ず“無我的理解”による解体が行われるべきものだった“世界観”を独自の浄土思想という様式において、「世界観の解体を経ることなく相対化する」という方法を選んだのが浄土仏教であると思います。
無我的理解には修行というコストがかかりますから、一般民衆の救済に重きを置いた浄土仏教宗派ならではの様式だったのでしょう。
もちろんこれは禅宗僧侶としての私個人の一方的見かたと言われても仕方のないことですが、著者のおっしゃるように、「無我」と「物語」とは少なくとも修行の上で本来両立が難しいものであるのは確かです。
著者のいうように「物語」とは取替えの効かない現実そのものですから、「物語」と思ってしまっては本来の「物語」とは言えないはず……という点も気になりました。
本来の「物語」を認識するためには「物語」の相対化をする必要があるのですが
相対化された「物語」が果たして本来の「物語」通りの強固さを保つのでしょうか……。
詳しくは本書を実際に読んでいただきたいのですが、もちろん宗派ごとのとらえ方によるものですから、本書の内容に直接かかわる問題点ではありません。
あまり声を大にして語られることのない「物語」について書かれた本ということで、多くの人に読んでいただきたい一冊でした。

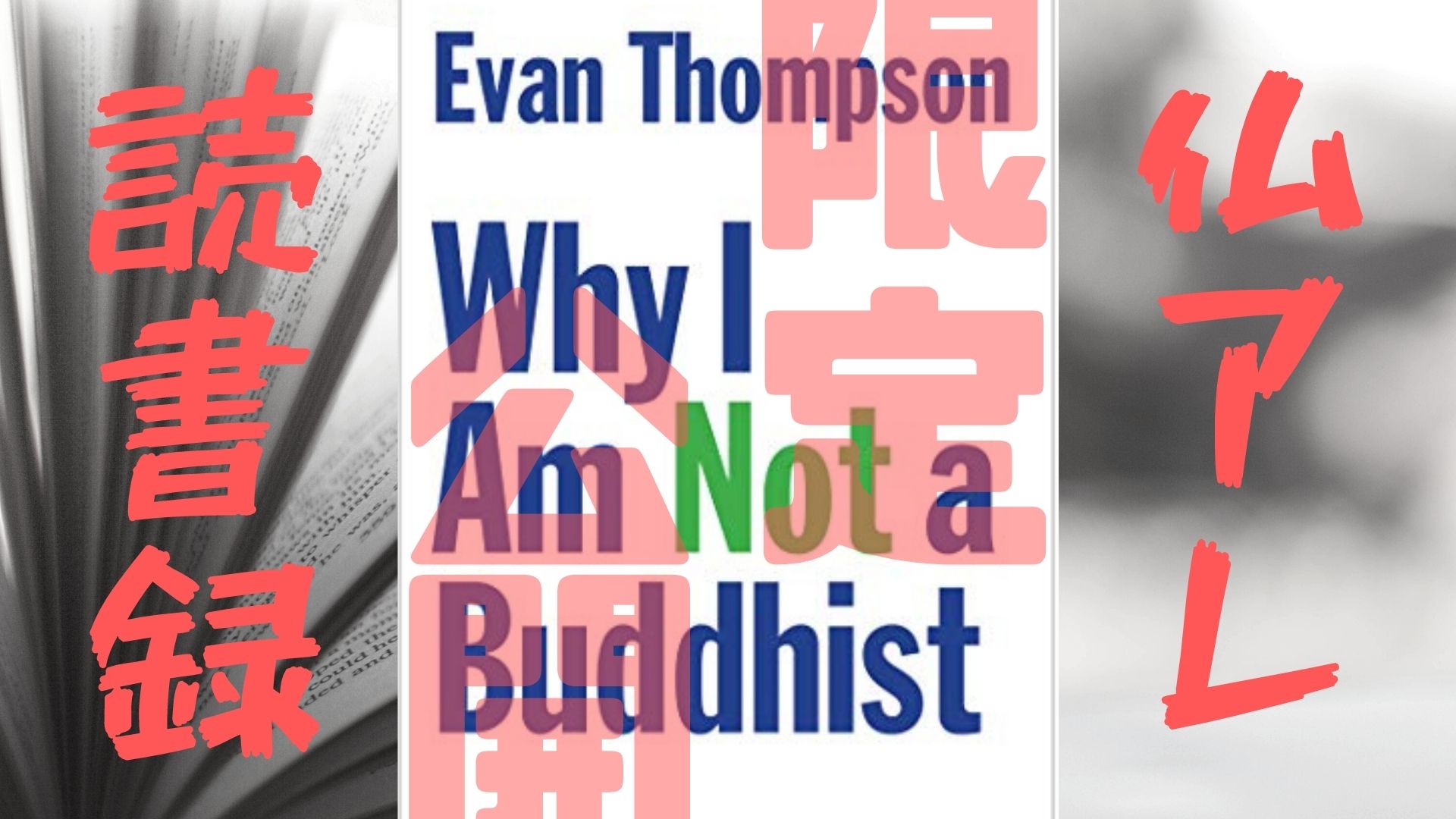


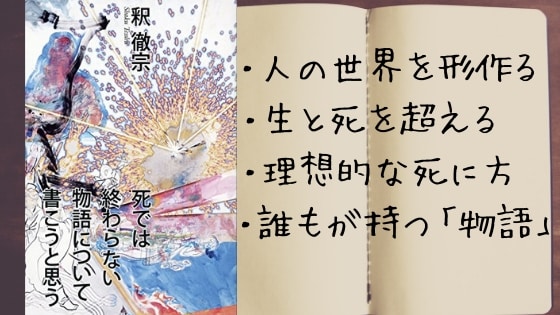
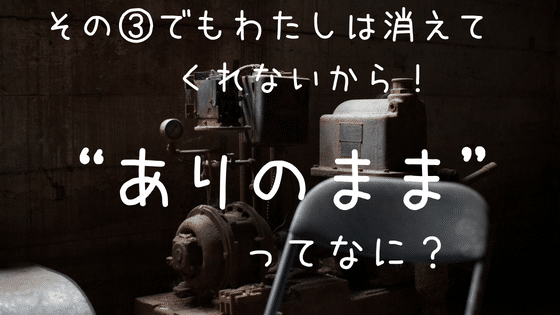
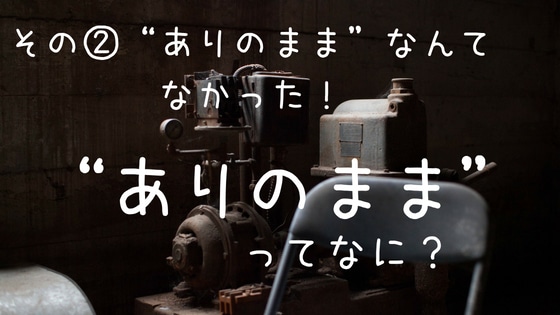
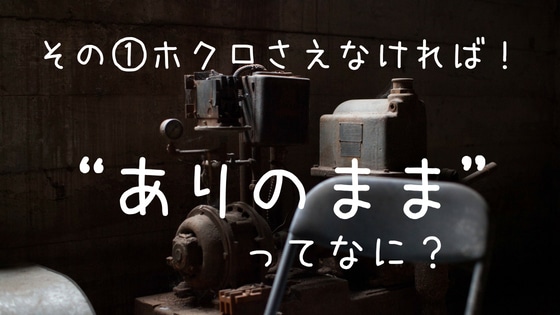



 「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

コメントを残す