|
僧侶の藤田一照さん、山下良道さんと哲学者の永井均さんが鼎談された本です。 藤田一照さんと山下良道さんは『アップデートする仏教』の中で、これまでの仏教とは違う〈仏教3.0〉ということを提唱し、現在もその活動を続けておられます。 哲学者の永井均さんは、〈私〉を哲学としてテーマにされ、書籍も多数出版されています。 また仏教にも造詣が深く、ご自身なりに仏教を解釈して、ここでは新しい仏教理解の枠組みを提案しています。 今回の鼎談は、その永井哲学と仏教の関連ということがメインになります。 お三方の問題意識が重なっており、奥深くスピード感のある内容に仕上がっています。 |
この本を読まれる前には、お三方に関するある程度の知識、問題意識をインプットしたほうがわかりが断然よく、面白いものになるかと思います。
藤田師、山下師が提唱する仏教3.0に関しては『アップデートする仏教』、両者のその他書籍を参考にしてみてください。
永井氏の哲学に関しては、近年出版された『存在と時間 ――哲学探究1』、『世界の独在論的存在構造: 哲学探究2』がおすすめです。
より易しい入門本も多数書かれているので、そちらも面白いです。
藤田師、永井氏の本は以前このサイトでもレビューしたことがあるのでそちらをどうぞ。
〈私〉と「私」
この本の大きなテーマは「瞑想の主体」です。
「誰が瞑想するのか」という、これまでの仏教の枠組みでは捉えそこなっていたことを、この本では永井哲学と交えて徹底的に論じています。
三人の主張を比較するとこうなります。
| 藤田一照 | 山下良道 | 永井均 | |
| 非本来的 | 有心のマインドフルネス | 雲 | 「私」 |
| 本来的 | 無心のマインドフルネス | 青空 | 〈私〉 |
*永井均さんに関しては非本来的、本来的という価値判断はしておらず、単なる区別であるとしています。
また、藤田一照さんの場合は、「主体」というよりもその主体が瞑想した際の「行為の状態」を指しています。
ここではそれぞれを細かく紹介することはしませんが、代表として永井氏の哲学をお借りして、簡単に説明したいと思います。
まず、どのようにして私と他者と区別しているのでしょうか。
考えてみればわかるように、属性(男とか、日本人とか、甘いものが好きなど)を使って他者と区別してはいません。
つまり「自分は他者とは異なる属性をもっているから、他者と違うのだ」と考えてはいないはずです。
例えば、”自分と全く同じ属性をもった人間”を仮定してみます。
それは完璧に自分をコピーした人間であるから、第三者が私とその人間を誰かに紹介するときには、どんな属性を語ったとしても、他の人からは区別することができません。
しかし、自分と寸分たりとも違わない相手が、自分の前に立っていたとしても、私はこう思うでしょう。
「”自分と全く同じ人間”が他者として、いる。」
つまり、すべての属性・性質・本質が同じ人間でも、私の場合だけは明確に他者を区別することができます。
このような何の属性であろうと関係なく、ただ直接的に実存しているもの、それを永井均さんは〈私〉と名付けています。
反対に、平板な世界解釈のなかで「私は~である」という形式で区別せざるを得ないものを、「私」としています。
ですから、今この記事を書いている「私」(道宣)を例に挙げると、「男で、日本人で、梅干しが好きで、僧侶である道宣」は、
〈私〉≠男、日本人、梅干しが好き、僧侶、道宣(そのもろもろの属性)
「私」=男、日本人、梅干しが好き、僧侶、道宣(そのもろもろの属性)
ということになります。
瞑想の主体
通常は上記のような〈私〉と「私」の峻別を意識的には行っている人は少ないでしょう。
大抵は〈私〉と属性を同一視しています。
その状態で、仏教の坐禅や瞑想を行うと、「私」が瞑想することになります。
この本では、瞑想の指導者である藤田師と山下師は、〈私〉が主体となって行うのが正しいのであって、「私」で瞑想してしまっては、本来的な瞑想にならないとします。
以前、友人の僧侶が仏教に興味がある人から、
「仏教の人はマインドフルってよく言うけど、仏教的にはマインドレスじゃないのか?考えちゃだめなんじゃないの?」
と質問されたことがありました。
「マインド(mind)」という単語を調べてみると、「身体と区別された(思考・意志などの働きをする)心、精神、(感情・意志と区別して、理性を働かせる)知性」と書かれています。
確かに、日頃から仕事で、思考や感情や知性をフルに使っているからヘトヘトに疲れているのに、瞑想までそれらをフルに使え、というのは違和感があります。
この誤解は、「マインドフル」の主体が〈私〉ではなく「私」であると、みなしてしまうことで起こります(〈私〉と属性の同一視)。
もし「私」が瞑想してしまえば、これまで日常生活と全く同じように、瞑想することでストレスを感じ、それを何とか取り除こうとして躍起になり、うまく取り除ければ喜び、失敗すれば落ち込みます。
そして忘れたころにまたストレスを感じ、それを取り除こうとし・・・・・・と通常の意識と同じように終わりのないループに入ってしまいます。
しかし、〈私〉と「私」の明確な区別がついていれば、思考、感情、知性などは属性であり、〈私〉ではないことがわかります。
(思考、感情や知性がなくなったと仮定しても〈私〉はそれとは関係なく存在することができます。)
そして〈仏教3.0〉では、本来的にマインドフルであるべき主体とは「私」ではなく、〈私〉であるべきであるとしています。
つまり本来的な瞑想状態は「〈私〉(マインドでない)がマインドフルである」という奇妙な表現にならざるを得ないのです。
そのため、藤田一照さんは「私」が落ちている坐禅的な状態のことを「無心(マインドレス)のマインドフルネス」という呼び方をしています。
「無心」って英語にしたら「マインドレス(mindless)」ですよね。
心がない。あるいは、no-mind。
マインドフルネスは文字通りの意味は「心がいっぱい」ですから、まさに正反対。
それが3.0では両立というかクロスしているところが、非常に禅的で面白いですよね。
無心がそのままマインドフルネスになっているようなあり方です。
このように、この本の基本的な主張は、「私」から〈私〉、雲から青空、有心から無心の転換(パラダイムシフト)を呼びかけているものになっています。
そのためにあらゆる角度からこの2項の何が異なるのか、どう実践まで結びつくか、ということを議論していることになります。
内山興正老師にかんして
本書では全三章の内、第二章をまるまる安泰寺の六世住職の内山興正老師の著作の中に見られる矛盾について議論しています。
正直この辺りは内輪ネタっぽくなってしまうので(藤田師、山下師、そして私たちも安泰寺出身)、深入りしたくはないのですが、内山老師は当時〈私〉問題に生ずる矛盾にぶつかっていたことがわかります。
それは「つながり(ぶっつづき)」と「断絶」です。
これは一切はつながっているという「つながり」は大乗仏教のテーゼともいうべき主張ですが、突き詰めていくと「断絶」が生じてしまい、「つながり」と辻褄が合わなくなるという問題です。
私の修行経験からも、非常に共感を感じたこの問題ですが、永井均さんはこれをうまく説明していると思いました。
簡単にいうと、計四段階の深まりを想定しています。
①「私」の断絶
通常の意味の孤立とか孤独です。
他人に理解されない、社会の中でもっとうまくやりたいのにできない、といった悩みが生じるような段階です。
②「私」のつながり
これも普通の意味で「私」のレベルで他者とつながるということです。
それも、コトバやお金といったある種の虚構によってつながりあうということです。
そこには、善悪・好悪・正邪・勝敗が存在する段階で、常日頃私たちが生きている社会そのものです。
相手を陥れて良くなろうとか、あいつのことが好き・嫌い、などがある世界観です。
③〈私〉の断絶
これはある種の質的転換が起こるポイントで、②の世界観を包摂しているといってもよく、①の断絶とは切れ方がことなり、〈自己=世界〉であるような段階です。
①、②のような舞台の上に投げ込こんでしまっている自己ではなく、他者というものがない自己ぎりの自己、と内山老師がよんでいるものです。
コトバでは「断絶」といいますが、内山老師はこの段階をポジティブに描いていています。
④〈私〉のつながり
そして、四番目は〈私〉のレベルでのつながりで、三段階目である人たち同士がつながることです。
これは内山老師がいっているような、根底がぶっつづきでつながっている、というものではなくて、永井氏は三段階目までいってから反転するという解釈をとっています。
ご本人は強い解釈が入っているとしているが、個人的には非常に面白い解釈だと思います。
この四段階目には、他者にも独在性があるという想定に立っています。
その質問に対して、永井均さんはこういっています。
永井 超越者ですね、超越性があるということですね。
これっていろいろな宗教的な考え方の中にある超越と同じですね
(中略)届かないものに届くっていうのがね。
届かないものとの繋がりこそが、本当の繋がりだと。
そうゆう宗教思想の原型のようなものがここから出てきますよね。
藤田 そういう根本的に届かないものというのが、本当の意味の他者なんですね
届かないところに届くことが本当の繋がりであり、これを慈悲とするならばそれは「祈り」のようなものであるとしています。
「慈悲の瞑想」もそうだけど、一種の祈りに近くなるんですよ。
「慈悲の瞑想」は一種の祈りですよね。
普通の言葉とは違うんですよ、日常の言葉とは。
転換への方法:揺さぶること
そして問題はいかにしてその転換を達成するか、ということです。
この本でずっと言われているような通常とは違う在り方があるよ、といってもほとんどの人は心から納得できないでしょう。
理解してもらうためには、「今自分が見ている現実のみが正しい」ということをいったん”揺さぶる”必要があります。
藤田師は喩え話で”北風と太陽”の話を使って、北風的な拒否反応、拒絶反応が起こらないような形で仏教を提供していくことを強調しています。
仏教の装いをしていない、まったく別の装いをしているけど、その本質は変わっていないような、その装いが防御反応を引き起こさないような仏教、「新しい皮袋に盛られた古の教え」みたいなことを、今ちょっと考えたりしています。
確かに、普通の人とは違う服をきて、頭もつるつるに仕上げているお坊さんという、いわば”異邦人”に「お前は本当の在り方に気づいていない(俺は気づいているが)」なんて言われたら、
カリスマ的な教祖にはなれるかもしれませんが、拒絶反応がでるひとは多いと思います。
そこで、太陽のように「気づいたら自然と服を脱いでいた」と実践者本人に思わせるような語り方が必要ではないかと提案してるのです。
仏教の語り方という問題
語り方ということに関連付ければ、先ほど、永井氏は他者に「超越性」がある、ということをいっています。
仏教に言及した、『世界の独在論的存在構造: 哲学探究2の付論』でも、〈私〉に関する超越性について言及しています。
また、別の書籍ではあるが、藤田一照さんと魚川祐司さんの『感じて、ゆるす仏教』の中でも、ある意味超越というのはキーワードになってくるでしょう。
しかし日本仏教の伝統的な仏教の指導者たちは、「超越」という言葉そのものにアレルギー反応というか、拒絶反応を示すことが多々あります。(例えば『超越と実存』の南直哉さんなどは顕著な例)
したがって、現代の日本仏教では超越という用語を使って何かを語るということがほとんどありません。
これは、要するに「超越論的観念論」というものを知らないとうだけのことですが。そういう意味では、どんな「覚者」でも(言葉で何かを言う以上は)もっと勉強しなければ駄目、ということになりますね。(もちろん、仏教系も同じですよ!)
— 永井均 (@hitoshinagai1) 2017年9月8日
特定の仏教指導者の発言に対してではないのですが、厳しいことを言われています。
なぜ仏教の人が超越を語らないのかといわれると、「知らないから」ではなく、「実践の面においてそれを語ることに対する弊害が大きいから」だと思います。
そしてその姿勢は仏教的に考えると確かに共感できるものがあります。
しかし僕個人は哲学・思想のつながりで最初に仏教に触れたこともあり、仏教の話を聞いていると、
「それって”超越”って言えば終わりじゃないかな。(別に”存在論的”に違う、でもいい)」
と感じることがありました。
当たり前のことですが一応断りを入れておくと、この本の中で山下師が指摘しているように、それらを自らの現実の中だけで受け止めてしまい、ただの知的情報処理のみが行われる危険性があります。
それを行わせないためにも、あえて語らないのだとは思いますが、個人的にはそればかりでは仏教の幅が狭くなる感覚があります。
その上で、もちろん伝統的な用語と論理を使って、仏教を深めていくことは絶対に必要だと感じています。
(ちなみに、”真理”批判もすでに伝統的になっています。)
しかし、海外の仏教を語る著述家も、科学や心理学といったこれまでとは異なる文脈で仏教を語りなおそうとしています。(『サピエンス全史』『ホモ・デウス』のユヴァル・ノア・ハラリや、『なぜ今仏教なのか』のロバート・ライト)
そしてそうでなければ、仏教が必要な人に仏教の面白さが届かない、と感じてしまいます。
私自身も初めて仏教に惹かれたのは、当時(ニコ生時代)魚川祐司さんがカントやハイデガーやおっぱいと絡めて語る仏教でした。
この話はこれまでが間違っていて、これからは「超越」を大々的に語るべきだといっているわけではありません。
仏教を固定的にせず、時代の中で本質を見据えた仏教を多方面から語る必要があるという、単純な話です。
それが許容されれば、相手を理解しないままに雰囲気だけで叩くという現象は起きなくなるでしょうし、
なにより多方面から語ることによって仏教の実践をしてみようという人が増えることは、とても喜ばしいことだと感じます。
その一つとしてこの本は、仏教を哲学という一つの面から見ようとした素晴らしい本だと思います。
この本は、こんなレビューだけでは終わらない面白さがまだまだ詰められた書籍ですので、ぜひ興味のあるかたは熟読してほしいと思います。

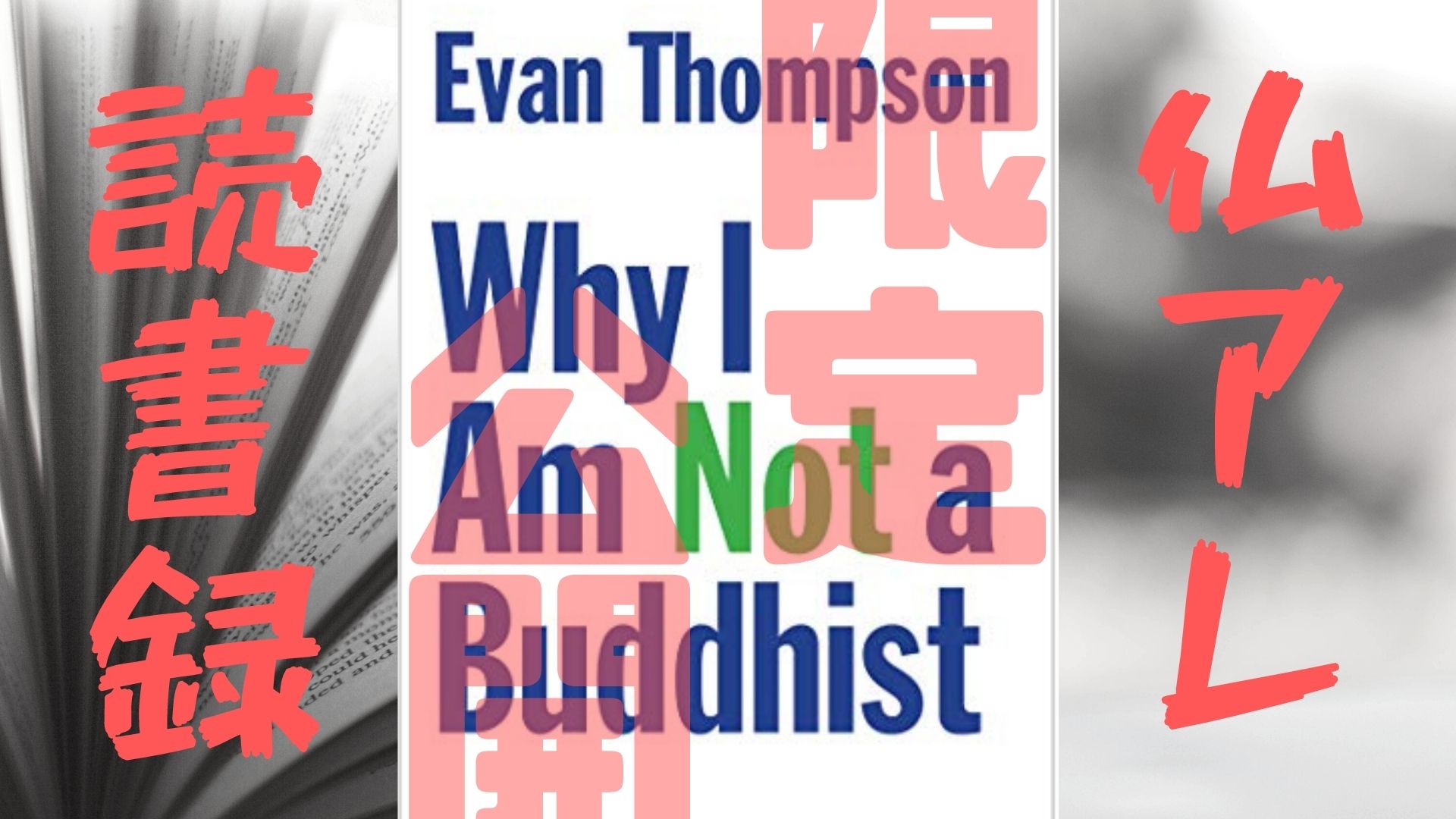


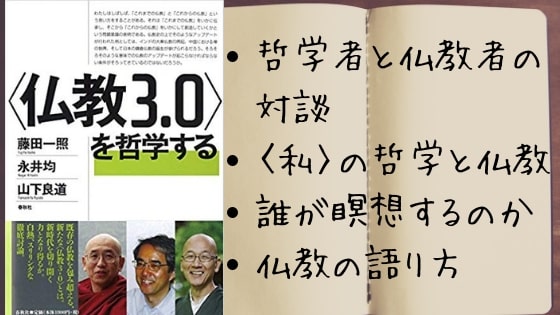
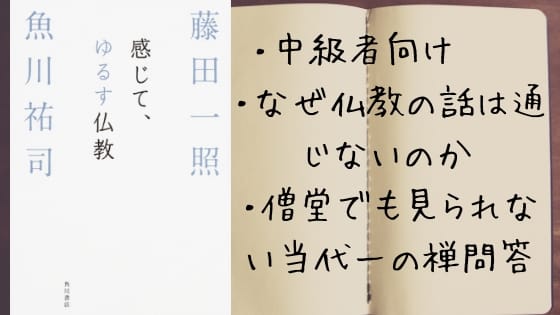
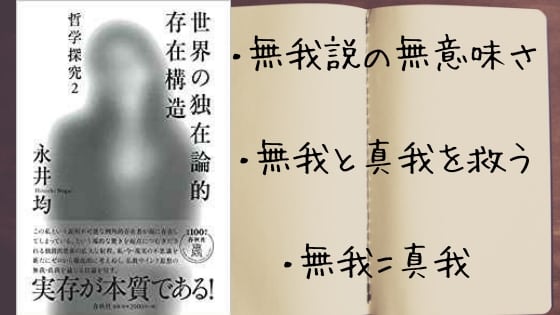




 「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

コメントを残す