|
仏教、とくに大乗仏教を学んでいるとかならず出会う「空」というキーワード。 その意味は歴史を通して一貫したものではなく、時代や地域によって意味やニュアンスが異なったものとして扱われてきました。 本書は「空」という言葉の変遷を仏教史に沿って分析しています。 分かったようで分からなかった「空」が比較の中で浮き彫りになる思想史です。 |
空の思想史
今回は立川武蔵さんの『空の思想史 原始仏教から日本近代へ』についての感想です。
「空」といえば、日本人には般若心経の「色即是空」でおなじみかもしれません。
しかし、仏教の歴史をみると一筋縄ではいかない概念であることが見えてきます。
この本は、初期仏教から密教、時代や地域によって異なった意味をもって扱われる「空」について解説をしています。
仏教、特に大乗仏教は各学派が好きなように言葉を使う(ときには新しい言葉さえ作る)ため、かなりややこしい部分があります。
例えば先程あげた「色即是空」の解釈も、インドと中国(日本)では大きく違っています。
空といえば竜樹(ナーガールジュナ)というイメージがありますが、その後の仏教思想史では竜樹の語義とは必ずしも同じでない部分がかなりあります。
仏教の入門書では一括にして「空」を定義していることがありますが、もう少し深く突っ込んで学びたい人は、「空」の使用方法が様々であることに意識的になってもいいかと思います。
またこの本の最も素晴らしいところは、空思想がもつ意味を語ったところです。
つまり『なぜ「空」と言わざるを得なかったのか、何のために「空」をつかったのか』についてにフォーカスを当てながら、空思想を見ていくことになります。
正直なところ細かい教義に関しては興味の無い人は多少難解になるかと思います。
しかし、「空」思想のアウトラインとその意味については初学者でも面白く読めるのではないのでしょうか。
空とは?
「空」は一義的には言えないとしましたが、その単語の原義を見てみましょう。
「空」のサンスクリット語は「シューニャ」であるが、この語は「あるものを欠いているもの」つまり「中味のからっぽのもの」を意味する。
中味がなく、さらに中味を入れていた容器も最終的にはないというのが「空」の意味である。
つまり「空」はある容器に存する中味の存在を否定し、さらに容器そのものの存在をも否定するという否定作業を踏まえていると考えることができる。
私たちは通常、自分があって、自分の外にモノが確かに「存在する」と思っています。
しかし、空思想はその考えに対して真っ向から反対します。
神、世界、自己、つまりすべてを言語が尽きるまで否定しつくします。
仏教は一般には、絶対的な神の存在を否定するが、一方では人間がもちうる特性としての悟りが存することは認める。
ところが空思想は、悟りの存在さえも一度は否定する。
「世界もない、人間もない、さらには悟りもない」と空思想は主張する。
すなわち、空思想では否定の対象はすべてのものであり、しかもその否定の程度は徹底しているのである。
かなり過激なように見えますが、そのような考えが生まれたのはどうしてなのでしょうか。
著者は、仏教だけでなく、バラモン正統派の哲学に関する書籍も多数書かれていて、広い視野から仏教を捉えられている方です。
本書でも空思想が出現した考え方の特徴をバラモン正統派の哲学と仏教の比較を行いながら解説しています。
もう一度白い紙を考えてみよう。
この紙には、無色透明ではあるが基体として一つの場があって、その場には白色という属性があり、さらに大きさ、形、匂い、重さといった属性も存すると考えられる。
さて、これらの属性を取り除くことができたと仮定してみよう。
白色を取る、匂いを取り除き、重さを取るというようにして、すべての属性を取り除くことができたとしよう。
最後に何か残ると考える人もいるだろうし、何も残らないと考える人もいるだろう。
ここて言われているのは、何かがあって、そこから特徴(属性)をすべて取り除いた場合に最後には何が残るのか、という問いかけです。
結論としては、「何も残らない」というのが仏教的な見方です。
反対に、属性を全部取り除いた後にも、目には見えない、匂いもしない、しかし、それがなければ成立しないというような場が残る、というのがバラモン正統派的な見方です。
気をつけなければならないのは、ここで仏教的といっているものはあくまでバラモン正統派と比較した場合のインド仏教の話です。(そしてここでは空思想を確立させた竜樹に端を発する中観派をベースとしています)
ですので時代や地域が変わればバラモン正統派的な主張を持つ仏教も現れてきます。
徹底否定の目的
この本で最も強調されているところですが、空思想の論者はなぜすべてを否定するなんていうことを言い出したのでしょうか。
ここまでくると、まるでニヒリズムに近いものを感じてしまうかもしれません。
いや、むしろニヒリズムそのものと思われてもしかたがありません(実際にバラモン正統派からは中観派は虚無論者と呼ばれていたらしい)。
空思想はすべてを否定します。
否定している自分さえも否定します。
しかしなぜすべて否定するのでしょうか。
このような「否定の手」はあらゆるものに伸びているがゆえに、空は「まったき無」を目指しているかのように見える。
しかし、竜樹自身も述べているように、この否定作業は、否定を通じて新しい自己あるいは世界をよみがえらせるための手段なのだ。
空の思想は何ものも存在しないとのみいうのではなくて、否定の結果として何ものかがよみがえるということを主張しようとしている。
この否定の後に続く肯定が空思想の求めるものであり、さらにこの否定に続く肯定が空思想の実践の内容にかかわるのである。
よみがえり
空思想は全ての「よみがえり」を目的として、手段として全てを否定しているということです。
”よみがえる”ためには一度死ななければなりません。
そのために私たちは自分も含めたすべてを殺さなければなりません。
徹底的なニヒリズム。
いや、ニヒリズムさえも否定する否定。
それは「よみがえりの後の世界」を私たちに見せるために、空思想の論者たちが用意周到にしかけた罠のようなもの。
「よみがえりの後の世界」については一切語らずに「よみがえらせる」ことを至上命題としてすべてを否定したのです。
では、なぜ彼らは「よみがえりの後の世界」を直接語ることを避けたのでしょうか。
空の思想はどうしてすべてを「無い」としたのか。
竜樹は業と煩悩は分別、すなわち概念作用から生じると考えた。
これらの概念作用は、プラパンチャ(戯論)から生じる。
よって、プラパンチャを止滅させることにより概念作用がなくなり、概念作用がなくなることによって、業や煩悩がなくなるというのが竜樹のいわゆる「縁起説」であった。
そのようにして世界が存在しないと知ることが、空の実践の前提条件であった。
このために空思想は徹底した否定の作業の必要性を説いたのである。
空思想を確立した竜樹によれば、悟りへの障害は「言語(プラパンチャ・戯論)」であり、それを取り除かなければ「よみがえりの後の世界」は現れない、ということです。
空思想の二面性
ここまできてわかるのことは、空思想には2つの側面があることがわかります。
- 「空」は全てのモノの存在や言語活動を否定するという否定性
- その否定の結果として新しい自己(世界)がよみがえるという肯定性
著者によれば、空思想の歴史は、この二面性のどちらを強調するかによって様々な意味や解釈が生まれたとしています。
そして、大まかに言えば、否定性を強調したのが、初期仏教や初期・中期大乗仏教であり
後期大乗仏教や中国・日本の仏教においては肯定性が強調されたとしています。
例えば『般若心経』には「色即是空、空即是色」という有名な表現がある。
これはこの経典がインドで編纂された当時は、「色即是空」とは「色つまり、色や形のあるものは無常のものであるゆえに執着するな」ということを意味したであろう。
しかし、中国や日本では『般若心経』のかの表現は、「色や形のあるままにもろもろのものは真実である」、すなわち「諸法実相」という意味であると解釈されることが多くなった。
つまり、インドでは「空」の否定的側面が強かったのに対して、中国・日本では空の肯定的側面が強調されるようになったのである。
空の実践:修行―時間
空思想は単なる概念操作ではなく、実践を伴った行為です。
この本では行為の三要素として、①世界観、②目的、③手段をあげています。
なにか行為を起こすときには必ず「どのような世界観で、何を目的として、どのように行うのか」が想定されます。
さらに著者は、行為の時間には三種類の時間があるといます。
- 目的が達成される前(悟る前)
- 目的が達成された瞬間(悟り)
- 目的が達成される後(悟りの後)
もちろん目的が達成されたら終わりではなく、その深まりというものがあるため、一回限りということはありません。
そしてこの中で、「目的―手段」という、「ここからどこかへ型」では語れないところも宗教には入ってきます。
世界観、目的、手段という区分けではなく、全て一つになったかのような瞬間というものは、歴史上の宗教者も示唆したり、現代の仏教指導者もそのような旨を語ることはよくあります。
それは空思想の論者が否定した言語を離れたものであり、「悟り」と呼んでもいいかもしれません。
しかし、すべてのどんな状況においても「目的―手段」を否定する言説を押し通そうとすることに関しては注意が必要でしょう。
確かに、最高真理は言葉を離れたものであるが、実際に生身の肉体を持った実践者は、言語に依った世間的真理の世界を生きています。
熟達した実践者の世界が、曹洞宗の開祖道元が言うような「諸法の仏法なる時節(すべてのものが仏教的真理である時)」に現実に生きている実感があることは察することができます。
しかし、特に初学者などは、自と他が別れた世界しか知らない状況から実践を始めなければなりません。
そこでは、実践者に対して言語を用いるのであれば相手が今どのような実践の時間軸にいるのか、見極めた上で言語を用いる必要があるということです。
そしてこの問題意識は、『空の思想史』の中で言っても、言語をただ否定しているだけではなく、いかに運用するか、という課題に変わっていきます。
空の思想史とは否定されるべき言語をいかに用いるか、という明敏な感覚に裏打ちされた歴史ともいえるでしょう。
まとめ
- 空思想のポイントがわかる本
- 細かい教義の違いとかも興味があるひとはどうぞ

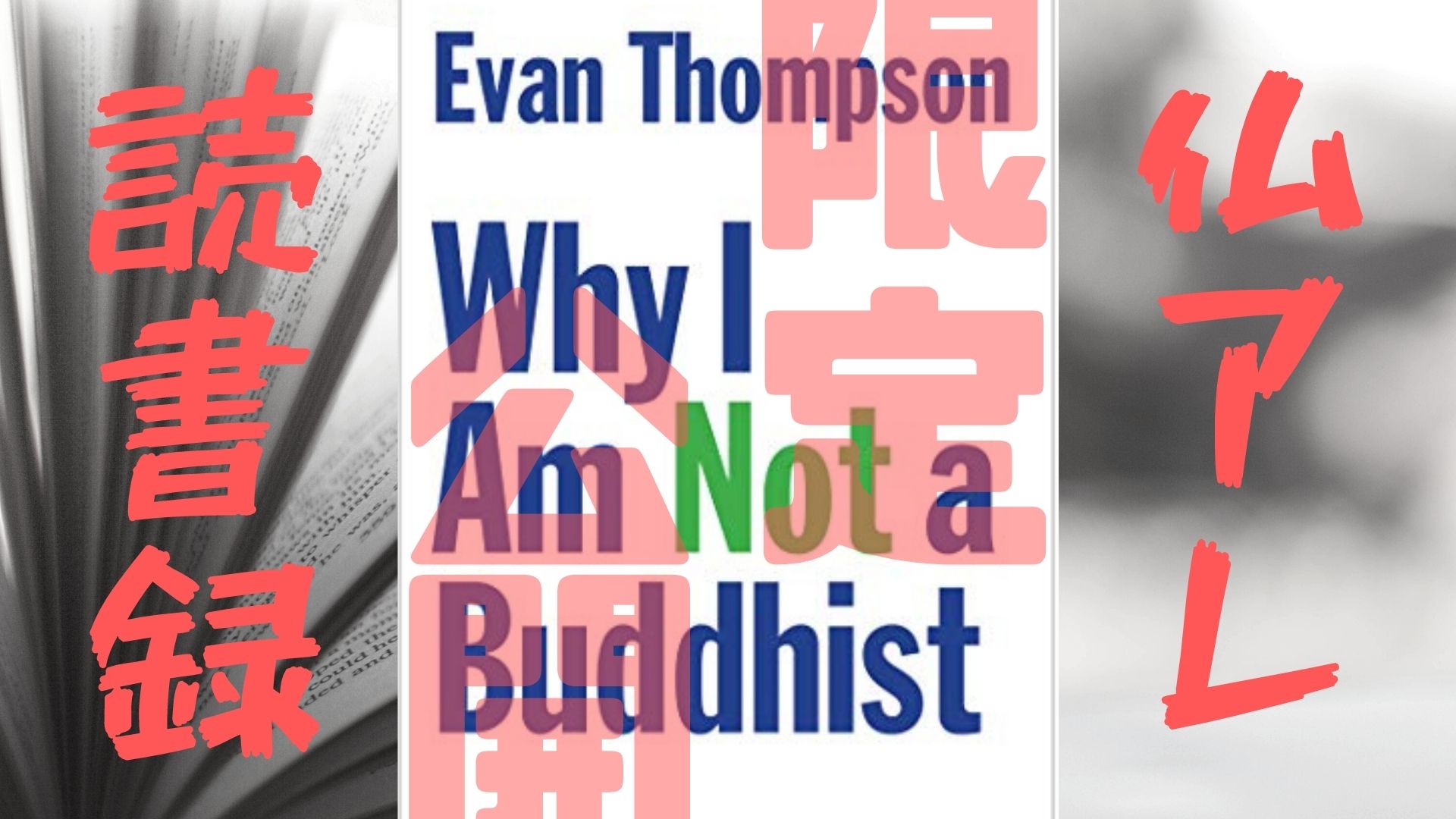


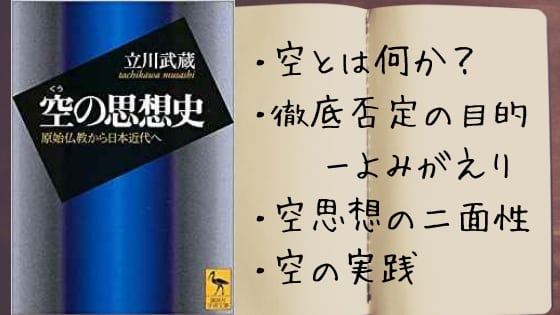


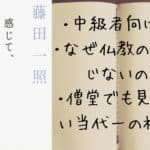
 「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

コメントを残す