|
国内販売累計70万部を超え、異例のヒット作となった 前著『サピエンス全史』に続く、これからの人類についての本作。 多方面からの情報と歴史学上の考察による十分な説得力によって ホモ・サピエンスの歴史上の立ち位置、つまり現代の人類を 明確に描き出した前作でしたが、その路線の魅力をそのままに、 現代を超えた未来の考察を中心に、これからの予想と抱くべき疑問を提出する力作です。 |
人間が向かわざるを得ない未来
イスラエルの歴史学者である著者は、人類の歴史に多方面からメスを入れ、多くの具体的で分かりやすいデータと例えによって考察を裏付けます。前作『サピエンス全史』をこれまでの人類の話とするのであれば、今作『ホモ・デウス』はこれからの人類の話になっています。
歴史上人類が苦しんできた飢餓、疫病、戦争などの大問題がほとんど解決に導かれました。
その一方で更なる科学技術の発展によって人類が向かわざるを得ない方向の先には、人類を超えた存在、「ホモ・デウス」の出現があると著者は言います。
「ホモ・デウス」とは、ホモサピエンスと一線を画した新人類のことです。
不死と至福の追求によって、人類を神へアップデートするプロジェクトを説明するために使われており、人類の子孫の一部が到達するであろう存在とされます。
とはいえ、著者が言いたいことは、この「ホモ・デウス」の出現についてではありません。
歴史学者である著者が強調する本書の狙いは、歴史を振り返ることによって歴史から解放されることにあります。
歴史の研究は、私たちが通常なら考えない可能性に気づくように仕向けることを何にもまして目指している。
歴史学者が過去を研究するのは、過去を繰り返すためではなく、過去から解放されるためなのだ。
つまり、人間を神に近づけるほどに進歩をし続ける科学技術と経済機構の中で、われわれが知っておくべき研究とその影響を踏まえることで未来を考えよう、と言うのが著者のスタンスです。
未来を選択するためには予測が不可欠である
本作で示される未来の予想図は、著者が最も考えやすい可能性としての未来であり、予言ではないとしています。
実際に、豊富な参考例をもとに提示される予想の数々が大きい説得力を持っているため、その他の可能性を自分で考えることが段々難しくなるほどです。
この予測は、予言というよりも現在の選択肢を考察する方便という色合いが濃い。この考察によって私たちの選択が変わり、その結果、予測が外れたなら、考察した甲斐があったというものだ。予測を立てても、それで何一つ変えられないとしたら、どんな意味があるというのか。
どんなに正しい未来の予測をしようと、それを踏まえてしか未来は作られないのだから、新たな予測は無限に可能になります。
とはいえ、現状の把握として著者が提出する予測は極めて納得のいくものであり、人類の向かうべき道すじを丁寧に描き出しています。
そのエキサイティングな内容については是非本書を読んでいただけたらとおもいます。
このレビューで強調したい本書最大の魅力は、“人間”を問い直す契機を作ってくれるという点です。
われわれ全員がそうであるところのホモ・サピエンスとは何か。
ひいては、サピエンスをも凌駕した末に出現する「ホモ・デウス」を踏まえて考えるべき人間とはなんなのか。
この点についてを読者に考えさせるための著作として前作以上に優秀なものになっていると思います。
科学によって解体されてゆく“人間”とその意識
著者が提出する中で最も大きい問題意識のひとつは人間の意識についてのものです。
生物とはアルゴリズムであり、生命はデータ処理であるという最新科学の定説を踏まえて、人間がそれに還元されるべきものであるのか。
事実、人間の知能面は既にAIによって徐々に先を越されているため、AIには無い独自の知能を人間が持つことは無くなってゆくだろうとされます。
その上で最新の生物学が「人間の意識は“全て”単なるアルゴリズムによって成り立っており、データ処理の一環である」という研究結果を提出した場合、われわれの日常生活はどのように変わってゆくのでしょうか。いや、それ以前にわれわれはどのように考えるでしょうか。
前作でも強調された、人間の意識を構成する要素の一つ「共同主観(虚構)」について考えることが、上記のような大変難解な問題に直面した場合に重要となります。
一般的に、われわれの意識は主観と客観によって成り立っているとされます。
著者が前作で大きく扱った、意識を構成するもう一つの要素である「共同主観」は7万年前にホモサピエンスを地球上最強の生物にした原因である革命的発見だったと著者は言いました。
- 私以外には誰もわかることが無いモノをあつかう「主観」
- だれもが具体的な形で確認可能なモノをあつかう「客観」
に加えて
- 誰も具体的には確認できないが、共有者の中では存在するとされるモノをあつかう「共同主観」
こそが人類特有の発明だったとしています。
「会社」や「神」「お金」などがこの「共同主観」に含まれます。
この「共同主観」のおかげで、距離が離れていようが、人数が多くなろうが行動を協力的にすすめることが出来たことで、人類は地上を征服したのだと「サピエンス全史」では語られていました。
現実世界に史上最大の影響力を持つ“意識”
本書で語られる最も衝撃的な予測は、この「共同主観的世界」が「客観的世界」と同一化してゆくだろうというものです。
それは、客観的現実を扱う生物学と共同主観的現実を扱う歴史学が同一化することと同時に起こると著者は言い、
この同一化は、「歴史上の出来事に生物学的説明が見つかるから」ではなく、歴史の流れに存在する政治的関心や経済的関心が、客観的世界であるDNAを書き換え、天候を再設計するような形で行われると予測されています。
つまり、(共同主観的に)思い描いたように客観的現実が作りかえられてゆく、ということです。
単にこう言われるだけでは、単なる荒唐無稽な話に聞こえるだけですが、
例えば、受精卵の遺伝子コードを操作する研究を例にとって説明されると、大きく説得力をもった話となるのが本書の特徴です。
デザイナーズベイビー(受精卵の遺伝子操作)は、もはや未来の話ではないのは確かです。
なぜそれが行われるのかを考えると、利用者がそれを善いとするからです。
その基準には「健康な身体をもって生まれることが幸せ」であるとする共同主観が不可欠なのです。
共同主観的現実は客観的現実を飲み込み、生物学は歴史学と一体化する。そのため、二十一世紀には虚構(※共同主観のこと)は気まぐれな小惑星や自然選択をもしのぎ、地球上で最も強大な力となりかねない。したがって、もし自分たちの将来を知りたければ、ゲノムを解読したり、計算を行ったりするだけでは、とても十分とは言えない。私たちには、この世界に意味を与えている虚構を読み解くことも、絶対に必要なのだ。
われわれの意識を形作る「共同主観」の影響力を強調する著者ですが、その意識を読み解くことが未来を選択するうえで、かつてないほど重要になると言います。
私たちは二十一世紀にはこれまでのどんな時代にも見られなかったほど強力な虚構と全体主義的な宗教を生み出すだろう。そうした宗教はバイオテクノロジーとコンピューターアルゴリズムの助けを借り、私たちの生活を絶え間なく支配するだけでなく、私たちの体や脳や心を形作ったり、天国も地獄も備わったバーチャル世界をそっくり創造したりすることもできるようになるだろう。したがって、虚構と現実、宗教と科学を区別するのはいよいよ難しくなるが、その能力はかつてないほど重要になる。
所感
歴史を振り返るときに「共同主観」という視点を採用したことが大変面白かった前作ですが、
その人間の意識を形作る「虚構」を踏まえて、その運用についての話を進めた今作は、前作以上に楽しめました。
※「共同主観」の一部である「物語」の重要性についてはこちらの記事でも書いてます。
その「虚構」自体が世界を形作ってゆく(あるいはもうすでに形作られている)という指摘は、
現代人にとってはギクッと気づかされる点も多々あると思います。
スマートフォンや医療、都市のインフラ改善などがどのように我々の日常に影響しているかを考えると、
人間が現実に適応しているというよりは、人間が現実を創り出しているという面も多いのではないでしょうか。
では、その現実を形作りはじめている“意識”とは一体なんなのでしょうか。
著者も謝辞の初めに挙げているように、著者は海外で有名なヴィパッサナー瞑想の指導者であるゴエンカ氏の下で仏教の実践を行ってきたようです。
著者自身の“意識”に対する分析と考察は、いうまでもなく
この仏教実践に大きく影響を受けていることは間違いありません。
だとしたら、著者の提出する
「意識に価値はあるのか」
という問題に対しては、著者が本書の中で言及することは無いものの、ある程度の結論を持っているだろうと言えます。
著者も前作本作を通じていたるところで言及しているように、価値を生み出すのは“共同主観”自体です。(価値というのも大抵の場合、共同主観に含まれる)
つまり「意識に価値を見出す」とは、言い換えると「意識に価値があると思っている意識をもつ」ことになります。
仏教の実践を行った著者であれば、結論を言い表すのに最も適当な言葉が様々に浮かんできたはずでしょう。
「意識とその主体は“無我”であり、“縁起”するもの」
と言ってしまえば全てが済むはずですが、結論を言わずに、
その文脈を人文科学と自然科学の両面で語りなおすことに本作の意義と魅力が詰まっていると思います。
仏教側からみたとしても、本書に挙げられた生物学の言葉「生物はアルゴリズムであり生命はデータ処理に過ぎない」を、言い直されて「世界はアルゴリズムによって成り立っており(縁起)、データ処理の過程に主体となる実態は無い(無我)。」と仏教を説明されても文句は言えません。
そこで、お坊さんとして私が挙げられる著者と共通の問題意識は、科学によって明かされてゆく客観的現実を踏まえて、自分自身がそれに対応するための“意識”を、いかに意味づけるか、です。
つまり「縁起であり、無我である」と言われて、納得できないからこそ仏教の実践が存在するわけです。
どう納得するのか。という点を見極めるべきであると思います。
これを考える方法をしっかり考えようね!と言うことが著者の狙いであることは間違いないので、その点については仏教徒としてもろ手を挙げて賛成したいと思います。
著者がそう言わないように、私もそれが仏教に限るとは全く思いませんが、難しい問題であるのは確かです。
まぁ、何より衝撃なのは、原語では2016年に出版されているので、こんなことを今更、わたしが言ってもすでに時代遅れだと言われるであろうことなんですが……。
※仏教的世界観の根底である、無我についてはこちら!

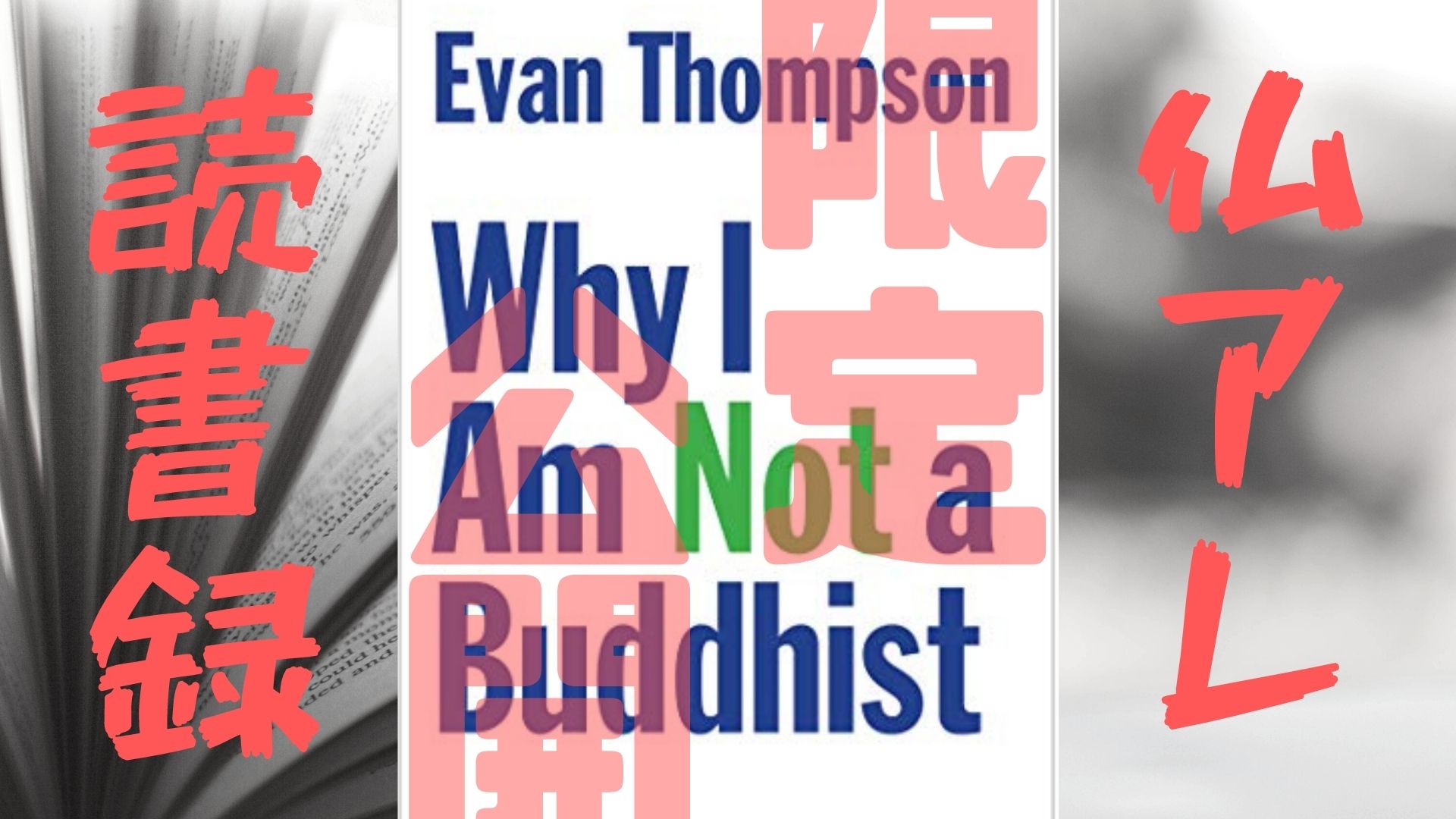



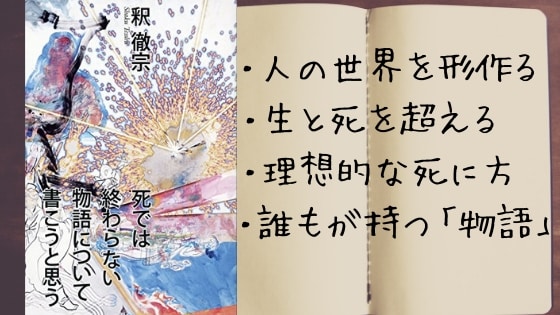





 「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。
「仏教のアレ」運営してるお坊さんです。禅とか修行ってそろそろアレじゃない?って思ってます。

コメントを残す